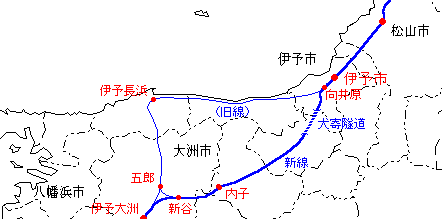内子線 <内子〜新谷>
|
<沿革>
1927年に讃予線の名称で松山まで開業した予讃本線は、1930年に伊予市まで、1935年に伊予長浜までが開業して愛媛線と接続し、予讃本線の高松〜伊予大洲間が全通した。 伊予市から先の予讃線の(伊予長浜経由の)海回り線は、「丙線(四級線)」として建設され、伊予長浜〜伊予大洲間は私鉄の愛媛鉄道を1933年に国有化したいずれも低規格の路線で、地滑り地帯を走る災害区間と言うこともあって運転上のネックとなっていた。 そのバイパス線として建設された内子経由の新線は、鉄道建設公団の手によって一級線規格(昔の特級線規格)で建設された近代的な高規格路線で、特急列車は平均100km/h程度で駆け抜ける。 伊予大洲から南西は1939年に八幡浜まで開業した後、1941年に宇和島〜卯之町間が開業した。 終戦間近の1945年6月に、最後の難所である笠置(かさぎ)峠を越えて八幡浜〜卯之町間が開通し、予讃線 高松〜宇和島間が全通した。 ただし、この時点では八幡浜〜宇和島間は宇和島線の扱いとなっており、この区間が予讃本線とされたのは、1947年以降1950年までの間と思われる(調査中)。 ・1947年6月1日改正時刻表  ・1950年10月1日改正時刻表 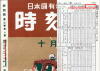 戦後の1950年に高松桟橋〜松山間準急として登場した「せと」が1951年に宇和島まで延長され、高松〜宇和島間の直通優等列車が誕生している。 一方、私鉄の愛媛鉄道が1918年に伊予長浜〜伊予大洲間を762mm幅のナローゲージで開業。1920年には、現在の内子線にあたる若宮連絡所(現伊予若宮信号場)〜内子間が開業した。 愛媛鉄道は1933年に国有化されて愛媛線と改称された後、1935年には伊予長浜で松山方面から伸びてきた予讃本線(当時は讃予線)と接続したのを機に、1067mmに改軌されるとともに、予讃本線に組み込まれた。 各区間の開業の時系列については「予讃線(1)」の<沿革>を参照。 <概要>
松山〜伊予市間は私鉄の伊予鉄道と競合関係にあるが、運転頻度と松山市中心部へのアプローチでは伊予鉄の圧勝、スピードと運賃ではJR優勢と両者決め手に欠け、結局は自動車利用が多くて鉄道の利用度は高いとは言えない。 かつて内子線は愛媛鉄道時代の名残で、元々伊予大洲(伊予若宮)から分岐していたが、1935年の改軌の際に線路変更が行われて五郎が起点に改められた。 改軌の際に一部でルートが変更され、現在もその遺構が一部残っている。 さらにその後1986年3月改正で開業したバイパス線は、新谷側から伊予大洲(伊予若宮信号場)側に取り付く線形に変更となった(この新線区間は予讃線として建設)ことから、旧内子線の新谷〜五郎間が廃止の扱いとなった。 そのため、現在の内子線は新谷を起点とした新谷〜内子間の路線ということになっており、「起点から終点方向に向かう列車が全て上り列車」になっている。 なお向井原〜伊予大洲間は、JRの旅客営業規則第157条により、「選択乗車」の適用対象区間となっている。 なので、例えば伊予市〜西大洲間の乗車券を購入した場合、運賃は安い内子経由で計算されているが、実際に乗車する区間は内子経由でも長浜経由でもどちらでもOKである。 <列車&車両>
列車は例によって特急と各駅停車の2種のみで、特急は全て松山運転所の2000系を使用した「宇和海」に統一され、下り17本/上り16本が運転される。 N2000系を主力として、アンパンマン車両などに量産車が充当されている。 2025年3月15日改正からは、八幡浜〜宇和島間でワンマン運転(都市型ワンマン)が開始された。 各駅停車は、伊予市折り返しの電車列車が松山運転所の7000系で運転される以外は、全て気動車列車となり、松山運転所のキハ32/54/185の各形式が使用される。 編成列車はキハ185系3000番台車が中心で、朝夕にはキハ32形とキハ54形の2〜3両編成も見られる。但しキハ185系は基本的に朝と夜のみの運用で、昼間は車庫で寝ていることが多い。 中心となる単行ワンマン列車はキハ32または54となるが、さすがにキハ32だと笠置越えや法華津越え、夜昼峠などの勾配区間ではかなり苦しげに登っている。 伊予長浜経由/内子経由とも毎時1本かそれ以下の頻度で運転されている。 所定編成では最長でも3両までで、トイレの設置されている車両が皆無のため、全ての普通列車がトイレ無しとなっている。 貨物列車は、2021年3月改正で南伊予駅横に設置された松山貨物駅までのコンテナ列車(高速貨B)が1日1往復運転されており、岡山機関区のEF210形が9両のコンテナ車を牽引している。 なお松山以南の区間の定期貨物列車は、国鉄時代の1984年2月改正で一旦全廃されており、松山貨物駅の開業により37年ぶりの復活となっている。 |
※駅名をクリックすると、各駅ごとの詳細情報のページを開きます
| 営業キロ | 駅番号 | 駅名 | (読み) | 開業年月日 | 電略 | 標高 | ホーム形態 | 主な施設 | 備考 |
| 194.4 |
Y55 U00 | (松山) | |||||||
| 197.9 | U01 | 市坪 | いちつぼ | 1964.10. 1 | チホ | 14 m |
対面 2面2線 | 駅舎無し | |
| 200.3 | U02 | 北伊予 | きたいよ | 1930. 2.27 | キイ | 14 m |
対面 2面2線 |
跨 待避線 | |
| 200.3 | - | 松山貨物 | まつやまかもつ | 2020. 3.14 | マカ | 17 m | − | ||
| 201.9 | U02-1 | 南伊予 | みなみいよ | 2020. 3.14 | ミイ | 17 m |
片面 1面1線 |
駅舎無し 松山運転所最寄り駅 |
|
| 203.0 | U03 | 伊予横田 | いよよこた | 1961. 4.15 | ヨコ | 12 m |
片面 1面1線 | 駅舎無し | |
| 204.8 | U04 | 鳥ノ木 | とりのき | 1986.11. 1 | トリ |
4 m (推定) |
片面 1面1線 |
曲線ホーム 駅舎無し |
|
| 206.0 | U05 | 伊予市 | いよし | 1930. 2.27 | イシ | 3 m |
併用 2面3線 | 屋跨 | |
| 208.5 |
U06 S06 | 向井原 | むかいばら | 1963.10. 1 | ムカ | 26 m |
片面 1面1線 | 高架駅 | |
| 211.6 | - | (三秋信号場) | みあきしんごうじょう | 1963. 2. 1 | ミキ | 80 m | − | (信号場跡) |
1986年3月廃止 ※営業キロは現役当時の数値を元に補正を加えた数値 |
| 213.9 | S07 | 高野川 | こうのかわ | 1963. 2. 1 | コノ | 32 m |
片面 1面1線 | 駅舎無し | |
| 217.1 | S08 | 伊予上灘 | いよかみなだ | 1932.12. 1 | カミ | 20 m |
対面 2面2線 | ||
| 222.4 | S09 | 下灘 | しもなだ | 1935. 6. 9 | シモ | 11 m |
片面 1面1線 | 昔は1面2線 | |
| 225.0 | S10 | 串 | くし | 1964.10. 1 | クシ | 20 m |
片面 1面1線 | 駅舎無し | |
| 228.2 | S11 | 喜多灘 | きたなだ | 1935.10. 6 | キタ | 13 m |
片面 1面1線 |
駅舎無し 昔は1面2線 |
|
| 233.1 | S12 | 伊予長浜 | いよながはま | 1918. 2.14 | ナマ | 3 m |
併用 2面3線 | ||
| 235.9 | S13 | 伊予出石 | いよいずし | 1918. 2.14 | イス | 8 m |
片面 1面1線 | 駅舎無し | |
| 239.3 | S14 | 伊予白滝 | いよしらたき | 1918. 2.14 | シキ | 8 m |
対面 2面2線 | ||
| 241.7 | S15 | 八多喜 | はたき | 1918. 2.14 | ハキ | 11 m |
片面 1面1線 | ||
| 243.4 | S16 | 春賀 | はるか | 1961.10.20 | ハル | 11 m |
片面 1面1線 | 駅舎無し | |
| 245.7 | S17 | 五郎 | ごろう | 1918. 2.14 | コロ | 14 m |
片面 1面1線 |
曲線ホーム 駅舎無し 昔は2面3線 |
|
| 247.1 |
- | (信)伊予若宮 | いよわかみや | 1986. 3. 3 | ワミ | 14 m |
信号場 交換設備無し |
||
| 249.5 |
U14 S18 | 伊予大洲 | いよおおず | 1918. 2.14 | オス | 15 m |
併用 2面3線 |
み旅 屋跨 | 留置側線有 |
| 251.6 | U15 | 西大洲 | にしおおず | 1961.10.20 | ニス | 20 m |
片面 1面1線 | 駅舎無し | |
| 253.5 | U16 | 伊予平野 | いよひらの | 1936. 9.19 | ヒノ | 23 m |
対面 2面2線 | ||
| 260.6 | U17 | 千丈 | せんじょう | 1639. 2. 6 | セチ | 26 m |
対面 2面2線 | ||
| 262.8 | U18 | 八幡浜 | やわたはま | 1939. 2. 6 | ヤハ | 7 m |
併用 2面3線 |
み旅 屋跨 | 留置側線有 |
| 267.5 | U19 | 双岩 | ふたいわ | 1945. 6.20 | フワ | 120 m |
対面 2面2線 | ||
| 272.4 | U20 | 伊予岩城 | いよいわき | 1945. 6.20 | イワ | 215 m |
対面 2面2線 | ||
| 275.4 | U21 | 上宇和 | かみうわ | 1945. 6.20 | カウ | 215 m |
片面 1面1線 | 駅舎無し | |
| 277.4 | U22 | 卯之町 | うのまち | 1941. 7. 2 | ウマ | 208 m |
併用 2面3線 |
み 屋跨 | |
| 280.0 | U23 | 下宇和 | しもうわ | 1941. 7. 2 | シウ | 203 m |
対面 2面2線 | ||
| 286.6 | U24 | 立間 | たちま | 1941. 7. 2 | タマ | 16 m |
島式 1面2線 |
留置側線有 曲線ホーム |
|
| 289.0 | U25 | 伊予吉田 | いよよしだ | 1941. 7. 2 | イヨ | 5 m |
対面 2面2線 | 跨 |
昔は2面3線 曲線ホーム |
| 293.9 | U26 | 高光 | たかみつ | 1941. 7. 2 | タカ | 29 m |
片面 1面1線 | ||
| 296.1 |
U27 G46 | 北宇和島 | きたうわじま | 1941. 7. 2 | キウ | 9 m |
島式 1面2線 | 跨 | 予土線分岐駅 |
| 297.6 |
U28 G47 | 宇和島 | うわじま | 1914.10.18 | ウワ | 2 m |
櫛形併用 2面3線 | み旅 | 旧宇和島運転区有 |
| 208.5 | U06 | (向井原) | |||||||
| 211.3 | U07 | 伊予大平 | いよおおひら | 1986. 3. 3 | ヒラ | 65 m |
片面 1面1線 | 駅舎無し | |
| 218.7 | U08 | 伊予中山 | いよなかやま | 1986. 3. 3 | ナヤ | 179 m |
対面 2面2線 | 屋跨 | |
| 225.4 | U09 | 伊予立川 | いよたちかわ | 1986. 3. 3 | タワ | 115 m |
島式 1面2線 |
曲線ホーム 駅舎無し 築堤上 |
|
|
232.0 <0.0> | U10 | 内子 | うちこ | 1920. 5. 1 | ウチ | 70 m |
併用 2面3線 |
み EV | 高架駅 |
| <1.6> | U11 | 五十崎 | いかざき | 1920. 5. 1 | イキ | 68 m |
片面 1面1線 |
駅舎無し ホームの端がトンネルの中に入っている |
|
| <4.1> | U12 | 喜多山 | きたやま | 1920. 5. 1 | キヤ | 21 m |
片面 1面1線 | 駅舎無し | |
| <5.3> | U13 | 新谷 | にいや | 1920. 5. 1 | ニヤ | 14 m |
対面 2面2線 | 駅舎無し | |
| <8.8> | - | (信)伊予若宮 |