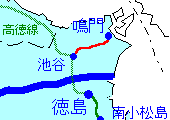MyTravel Vol.8
<JR四国線取材(?)紀行> その8
鳴門線 池谷〜鳴門間
<番外編>旧小松島線
12月15日(月)
シリーズとなったJR四国線レポートも、今回を97年版の最後として締めくくりたい。
最後まで残っていたのは、現住の松山から最も遠い、徳島県の鳴門線と牟岐線である。
当日は、自家用車にて朝4時50分に松山の自宅を出発、帰路は実家に寄り道しながら22時50分に松山に帰着、総走行距離670キロ/所要18時間に及ぶ行程であった。
実はこの前々日はNiftyのOFFがあって(→「DIARY Vol.26」)半徹夜状態であったので、前日は19時に寝たのである。
4時に起床してNiftyのログを取ってコメントをアップしておいてから出発。
新居浜までは国道11号線を通り、新居浜ICから三島川之江ICまで高速を利用。そこから国道192号線で池田町を経由、穴吹の手前で吉野川南岸の国道192号から北岸の県道に転線して、そのまま真っ直ぐ鳴門に向かった。
<鳴門線>
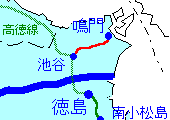
JR鳴門駅前に到着したのは、松山を発って丁度4時間後の午前8時50分。ここまで丁度200キロであった。
鳴門市は人口7万人弱、徳島県第2の都市である。鳴門海峡のうずしおで有名で、本四架橋・大鳴門橋が架かる。
鳴門線の開業は大正5年、阿波電気鉄道によって吉成〜撫養間が開業した。「電気鉄道」とは名だけで実際は蒸気鉄道であった。当時はまだ吉野川に橋を架けられるだけの技術が無く、吉成〜佐古間は鉄道連絡船が運航されていた。
鳴門と徳島を結ぶのに何故池谷方面を迂回する必要があったのかは謎だが、そのために現在の鳴門線は学生や老人などの利用するローカル線と化しており、徳島〜鳴門間を直結してしかも経路途中に徳島空港もある国道11号線はいつも盛況で、線路に雑草が生えている鳴門線とは対照的である。
JR鳴門駅は鉄筋平屋建ての割と簡素な駅であるが、実は徳島県内のJR線の駅で駅舎が鉄筋コンクリート製というのは、非常に少ない貴重な存在なのである。
鳴門線の駅は教会前や金比羅前など、元私鉄であったことが伺われる直接的な駅名が多いほか、終点の鳴門を除いた全駅が交換設備を持たないなど、ローカル色が強い。
現在はキハ40やキハ58・65による普通列車が1日16往復運転されており、一部ワンマン列車もあるが、ほぼ全列車が徳島まで直通する。
鳴門駅は開業当時は「撫養」と名乗り、それまでの撫養駅は「蛭子前」に改称されたが、後年になって現在の鳴門に改称され、その時に「蛭子前」も「撫養」に戻された。
かつては留置側線も有していたが、現在は島式ホームが1本あるだけで、その先は行き止まりである。
万が一大鳴門橋を鉄道が走ったとしてもこの先が延長されることは無かろう。
番外編
<旧小松島線>
かつて中田から小松島まで、わずか1.9キロの路線が存在していた。
国鉄合理化の嵐の中、昭和60年を持って廃止された小松島線は、もともとは徳島と小松島を結ぶ路線として開業した。
1913年の開業の4年後には国有化されており、中田から先牟岐までを結ぶ私鉄の阿南鉄道(後、国有化)はそれより随分後になって開業している。
1961年に徳島〜中田間は小松島線から牟岐線に編入された。結果、小松島線は盲腸線となり特定地方交通線第一次廃止対象線区に指定され、国鉄民営化を前に廃止された。
現在の中田を出ると、右にカーブする牟岐線に対してまっすぐ市街地に向かう遊歩道があり、これがかつての小松島線の跡である。
元の小松島駅、及び小松島港駅の跡は市民公園となっており、小松島駅跡地は「SL記念公園」として、小松島港駅跡は「たぬき広場」として市民に解放されている。
小松島港からは和歌山行のフェリーが連絡しており、今でも一日に数便が運行されている。
「SL広場」には、小松島駅をかたどったホームがあり、12型SLとオハフ50型客車が保存されている。
小松島には機関区と客車区があり、牟岐線や徳島線で使用されるC12形や、DE10形といった機関車のほか、スハフ43/オハ41といった希少旧型客車も配置され、配置直前の頃には50系客車が30両ほど配置されていた。