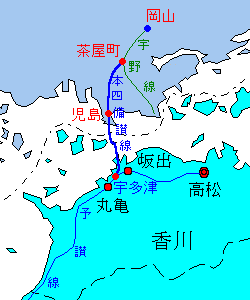MyTravel Vol.7
<JR四国線取材(?)紀行> その7
本四備讃線 茶屋町〜宇多津間
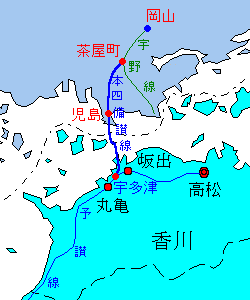
10月25日(土)
好評(嘘つけ(^^; )のこのシリーズも、残すところあと3路線。
今回はJR四国管内の路線では最も新しくて近代的な本四備讃線である。
一般に「瀬戸大橋線」と呼ばれているのは、宇野線 岡山〜茶屋町間/本四備讃線 茶屋町〜宇多津間/予讃線 宇多津〜坂出間を包括した「愛称」である。
「京浜東北線」と同じ類のものと思えばよい。
本四備讃線は1975年に、いわゆる「本州四国連絡橋 児島坂出ルート」の鉄道部分として着工、1988年の春に開業にこぎ着けた。
但し、最終チェックのために若干遅れて4月10日に開業した海峡部分(児島〜宇多津間)に対して、陸上部である茶屋町〜児島間は瀬戸大橋博覧会の開幕に合わせて一足先に3月21日から営業を開始した。
開業当初、1日の定期列車本数は特急9往復/快速19往復/貨物3往復であったが、現在(1997年10月1日ダイヤ改正時点)では、特急21.5往復/快速33.5往復/普通9往復/貨物5往復に増え、JR四国のドル箱的路線である。
橋を挟んだ対岸の児島と丸亀には公営競艇があるため、その開催日ともなるとオッサン連中が大挙して橋を渡る(^_^;
開催日が重なった日など、列車を使って競艇場の梯子をする人も結構いるらしい。
また、列車を使っての隣県通勤・隣県通学ももはや当たり前のようで、とにかくこの橋、もはや日常生活に無くてはならないモノとなっているのだ。
本四備讃線の起点茶屋町は、同線の開通を機に2面3線の高架駅に建て替えられた。両端の2線を瀬戸大橋線が使用し、中央の1線を主に宇野線や茶屋町〜児島間の区間運転の普通列車が使用している。
この中央の1線は両側にホームがあり、どちら側からでも乗り降りが可能で、上下の瀬戸大橋線列車と宇野線列車との乗換が便利な配線となっている。
この日私が児島から上の町まで乗車した単行列車は「クモハ123」と呼ばれる、かつての荷物電車を改造した車輌で、側面の扉や窓配置に独特のモノがある。この日乗車したのはその5号車で、車番表記は「クモハ123−5」
・・・・・・・続き番でなくてちょっぴり残念\火暴/
なおこの車輌、宇野線の茶屋町〜宇野間でも使用される。
茶屋町を出た線路は宇野線の単線をオーバークロスし、右手方向に緩いカーブを描きながら植松に向かう。
植松を通過すると全長約2155mの蟻峰山(ぎほうざん)トンネル。
トンネルを抜けたところにあるのが木見。そこを通過するとまたすぐにトンネル。
全長3652mの福南山トンネルを抜けると上の町。
そこを通過すると今度は全長1605mの児島トンネルで、それを抜けるとすぐ児島に着く。
この間、最急曲線は1200R、最急勾配10‰、全線スラブ軌道という新幹線並の高規格線で、しかも茶屋町から児島までは1本のロングレールで繋がっており、レールのジョイント音は聞こえない。
実際、この区間は将来新幹線を併設できるように設計されており、各種設備の建築基準も比較的ゆとりがある。
児島は2面4線のホームを持ち、しかも各線の構内有効長が600mと非常に長い。
これは、濃霧や地震などの非常時に、列車を抑止・滞留させておくためで、同一線内に10両編成級の列車を2本留めておくことができる。
また児島はJR西日本とJR四国の境界駅で、殆どの列車がここに停車して乗務員が交替する。
一部の特急列車は児島を通過するが、その場合は四国側の多度津・丸亀駅、又は坂出駅で交替する。
児島を出て神道山・鷲羽山トンネルを抜ける。このトンネル、2つのトンネルが一続きとなっているだけでなく、入口は1つで出口が2つに別れているという随分変わったトンネルである。
トンネルを出たところはもう海の上。海面上約50m、全長1447mの下津井瀬戸大橋である。
櫃石島高架橋(1316m)を渡り、櫃石島橋/岩黒島橋(いずれも792m)と2つの斜張橋を渡る。
続いて羽佐島高架橋(266m)からトラス橋の与島橋(877m)を経て与島高架橋(717m)で与島を跨ぐ。
与島を過ぎると、北備讃瀬戸大橋(1611m)/南備讃瀬戸大橋(1723m)の2つの吊橋を渡る。
この間約9.6キロ、これら9橋を総称して「瀬戸大橋」と呼び、列車はここをわずか5分で渡ってしまう。
この間、私にとってはもはや見飽きた光景だが、朝の日の出時にここを通りかかった際の景色の素晴らしさは割とお気に入りである。
橋を渡ると番の州高架橋を走り、松山・高知方面に直進する路線と高松方に分岐する短絡線に別れる。
ここは信号扱い上はもう既に宇多津駅の構内で、信号機にも「場内○番」の表記がある。
松山・高知方面に向かう特急「しおかぜ」「南風」などはそのまま直進して宇多津駅に至り、予讃線の下り線と合流。
快速「マリンライナー」や寝台特急「瀬戸」などは短絡線を経由して予讃線の上り線と合流し、坂出に至る。
宇多津新都市周辺はかつての塩田跡地で、瀬戸大橋開通当時はまだ周辺には何もなかったが、現在では「新都市」と呼ぶにふさわしい街になりつつある。