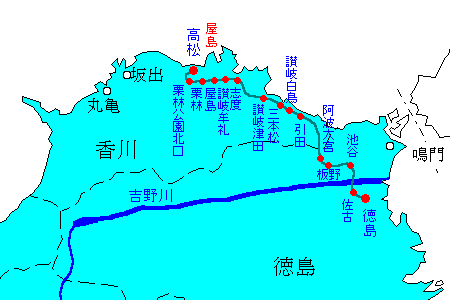MyTravel Vol.5
<JR四国線取材(?)紀行> その5
高徳線 高松〜徳島間
9月21日(日)
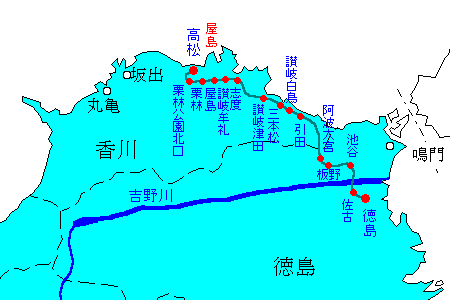
さて、本来であれば、翌22日の月曜日に、高松から高徳線回りで徳島経由で徳島線を巡り、そのまま香川の実家に帰る予定でいたのだが、時間的に厳しそうな予感がしたので、この日所用で高松に行った折り、ちょっと時間が余ったので高松から高徳線方面を少し進めておくことにした。
高松は予讃線の時に撮影したのでパス
高松を西に向かって出発した高徳線は、栗林までの間にU字カーブを描いて東に180度向きを変える。
そのU字カーブの底点(頂点?)にあたる昭和町は、踏切脇のスペースに取って付けられたような片面ホームのみの駅で、次の栗林公園北口と共に国鉄民営化の直前に作られた駅である。
この先、線路は高架となる。
栗林公園北口は、漢字で6文字、平仮名で12文字、ローマ字で21文字というJR四国内で最も長い駅名である。すぐ脇に神社があり、一瞬鳥居が駅の入口かと錯覚する。栗林公園の北口はここから歩いて3分ほど。
栗林は四国内で初めての高架駅。島式ホームが1本あるだけの駅だが、特急も殆ど全列車停車し、みどりの窓口もある。高松・徳島を除いた高徳線内の駅では最も乗降客数が多い。
この先線路は地平に下り、木太町。ここも昭和町や栗林公園北口と同じ日に開業した新しい駅である。
源平古戦場として知られる屋島の袂にある屋島。
島じゃないのに何故「屋島」? といぶかるかも知れないが、そこは昔はれっきとした島だったのだ。
屋島が香川県本土(?)と陸続きになったのは比較的最近のことで、香川県地図を見て貰えば解るが屋島の袂には東西に流れる川がある。この川、東と西の両方で瀬戸内海に繋がっている一見奇妙な川であるが、これが屋島がかつて島だったことを物語る証拠でもあるのだ。
次の古高松南、一つ置いて讃岐牟礼と、いずれも86年11月のダイヤ改正時に開業した駅で、この時の改正で四国内に誕生した10の新駅のうち、半分の5駅が高徳線高松口に集中していることになる。
志度は高松から約16キロ、普通列車で30分程度の距離にあり、近年は高松のベッドタウンと化している。
高松から志度までは私鉄の高松琴平電気鉄道(コトデン)と競合し、運転頻度では20分間隔で運行しているコトデンが、スピードと運賃ではJRが優位に立っている。
また、JR志度駅は四国内では予讃線の伊予三島に次いで2番目という橋上駅化工事が進捗しており、この当時はプレハブの駅舎で仮営業中であった。
みどりの窓口、旅行センターとも備え、特急「うずしお」も全列車停車する。乗降客数も栗林と並んで高徳線内では最も多い。
また、志度町は江戸時代の発明家、平賀源内の故郷でもあり、遺品館と旧邸が駅から徒歩7〜8分の所にある。
ここから高徳線は南に向きを変え、一旦内陸部に入る。造田、神前まで来たところで、この日は打ち切って実家に帰った。
9月22日(月)
さて、この日は本来なら讃岐津田からスタートする予定であったが、21日に高松市内のショップで購入したソフトが対応機種が違っていたために返品する必要が生じたことから、この日は実家から南に向かって県境を越え、徳島線の阿波池田側からスタートして讃岐津田まで行き、そのまま高松を経由して例のソフトの返品に行くことにした。
#ショップの開店時間の都合から
だが一応高徳線については、このまま讃岐津田から徳島に向けて書き進めていくことにする。
一旦内陸に入った高徳線は讃岐津田で再び海岸線に出る。津田は「津田の松原」で有名で、綺麗な海岸線が今も残っている。駅のすぐ近くに高校があり、この日は下校途中の高校生で賑わっていた。
#ぢょしこーこーせーが多かったような気がするのは偏見か?(火暴)
三本松は高松〜徳島間の丁度中間地点に位置する。
土讃線で言えば阿波池田、予讃線で言えば新居浜、徳島線で言えば穴吹のような駅で、いずれも特急列車が全列車停車するという共通点がある。
次の讃岐白鳥は、手袋の生産高で全国シェアの9割を占める白鳥町の駅で、駅の周辺にも手袋工場が立ち並んでいる。
引田は養殖ハマチの町。高松からここまで、概ね1時間当たり2本程度の普通列車が運転されており、高松からやってきた普通列車の半数はここで折り返す。
次の讃岐相生からは県境の大坂峠越えで、25‰の勾配で峠を越える。かつてのキハ58系急行「阿波」などは時速30〜40キロ程度で喘ぎながら登っていたモノである。
ちなみに駅名の読みは「ひけた」である。「ひきだ」等と読むのは何かの見過ぎでは?(^^;
峠を越えたところが阿波大宮。山間部に位置する寂しい駅で、1日の乗降客数は100人に満たない。
更に南に向かって勾配を下って、板野。ここからは普通列車の本数も若干増える。
板野からは、かつて鍛冶屋原線(かじやばらせん)が分岐していたが、1972年に廃止されてバスに切り替わっており、JRバス鍛冶屋原線は今も健在である。
ここから線路は東に90度向きを変え、池谷に至る。これも「いけたに」などと読んではいけない(^^; 「いけのたに」である。
ここでは鳴門線が分岐。ここから再度南に向きを変える高徳線のホームと、徳島方面から北上し、ここで東に向きを変える鳴門線のホームがまるで反発しあうように弧を描きながらV字型の線形を形成、そのV字の谷間の部分に駅舎が鎮座するという模型のようなレイアウトである。
ここからは鳴門線の列車も合流し、日中は1時間当たり2〜3本程度の普通列車が走っている。
南に向きを変えた高徳線は、吉成を過ぎると四国一の大河、吉野川を全長949mの吉野川橋りょうで渡る。
瀬戸大橋が出来るまでは四国最長、20年ほど前までは全国でもベスト10に入るほどの長大橋であった。
橋を渡ると佐古。ここはもう徳島市の中心部に近く、佐古駅は平成4年に高架化された。
ここからはさらに徳島線の列車も合流するため、わずか1.4kmながらも複線区間となり、日中は1時間当たり上下あわせて12〜15本の列車が行き交う。
この佐古〜徳島間は、以前は見かけ上は複線でも、実際は高徳線の単線と徳島線の単線が2本並んでいるだけであった。高徳線列車と徳島線列車のすれ違いは出来ても、高徳線列車同士や徳島線列車同士のすれ違いは出来なかった。
JRになったときにこの区間の信号設備が改良され、複線運転が可能となり、ダイヤ編成にも余裕が出来た。
高徳線の終点徳島は平成5年、四国では初の複合ターミナルビルとして生まれ変わり、メインである「クレメントプラザ」のほか、JR四国直営のホテル・クレメント・徳島も入居する。
発着列車本数・乗降客数・ホーム数いずれも人口で勝る松山・高知を遥かに上回り、四国内では高松に次ぐナンバー2のターミナルである。
駅に隣接して徳島運転所も併設されており、駅の正面には眉山、裏手には徳島城跡が構えている。