 | Vol.5へ |
MyTravel Vol.4
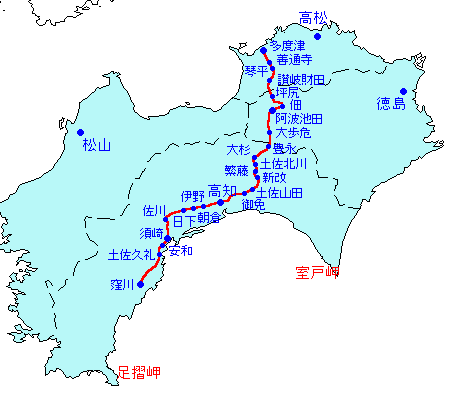
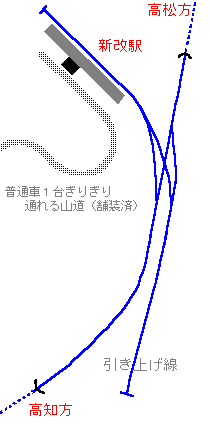
|
土讃線の無煙化 土讃線は特に琴平〜土佐山田間(約100km)にかけては急勾配とトンネルが多く、同区間の3割以上がトンネルで占められている。 加えて線路規格も高くなかったため、大型の機関車が入線できず、SL(蒸気機関車)時代は集煙装置を付けたC58形やD51形が使用され、乗客はもちろん乗務員も煙害に悩まされて、死者が出ることも少なくなかった。 そのため、昭和30年前後から全国的に始まった無煙化に際しては四国はそのモデル地区とされ、特に土讃線に優先的にDL(ディーゼル機関車)・DC(ディーゼルカー)が投入された。 昭和31年には電気式DLの試作機DF40(後のDF91)形が、翌32年からはDF50形やキハ55・20系といったディーゼルカーが大量投入され、土讃線 多度津〜高知間は早くも昭和34年秋には全列車の無煙化が達成され、乗客らは煙害から開放された。
|
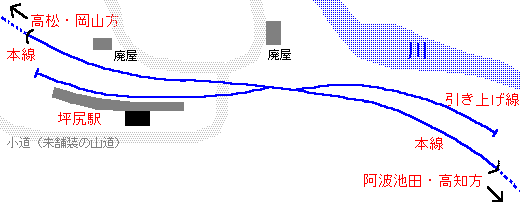
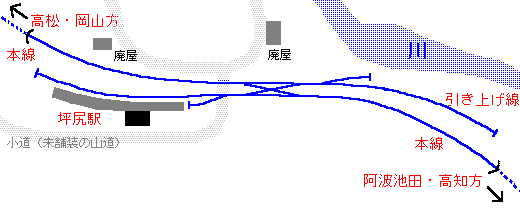
|
SL時代、貨物列車がこの猪ノ鼻越えにさしかかったとき、車掌が尿意をもよおした。当時の貨物列車に連結されていた車掌車はトイレが無く、かといって列車の速度が遅いので阿波池田まではまだ相当時間がかかりどうにも我慢できない。 そこで車掌は列車から飛び降りて線路脇で用を足し、それからまた走って列車を追いかけてそのまま飛び乗ったという、、、、 |