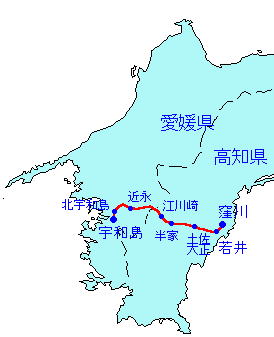宇和島から近永までは概ね1時間に1本程度の普通列車が運転されており、意外なほど利用客は多い。
出目あたりから、四万十川の支流である吉野川(徳島県の吉野川とは別物である)に沿って走り、真土を過ぎると県境を越えて高知県にはいる。
江川崎はかつての宇和島線の終点で、ローカル線には似合わないほどの広い構内と長いホームを持つ。
江川崎から先は、鉄道建設公団の手によって昭和49年に開業した比較的新しい区間で、四万十川に沿って蛇行する国道を横目に、鉄橋やトンネルで直線的に敷設された近代的な路線になり、列車の速度も上がる。駅間が結構長いこともあって最速列車の窪川〜江川崎間の表定速度は60km/h近い。
江川崎の次は面白駅名の一つ、半家(はげ)。この日見たときは、駅前の国道に建つ駅の場所を記す標識が剥げていて洒落にならなかった(^^;
土佐大正、土佐昭和と元号の名の付く駅が続く。
家地川の次は川奥信号場。ここが実質的な予土線と土佐くろしお鉄道の分岐点である。窪川側からやってきた列車はここで二手に分かれ、予土線列車は左側のトンネルへ、土佐くろしお鉄道の列車は右側のトンネルに入ってゆく。
地図の上の感覚からすれば逆なのだが、これでいいのである。なぜなら、、、、、
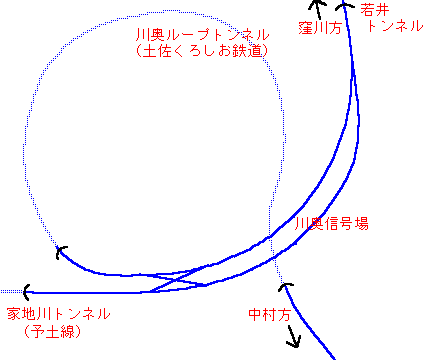
予土線は家地川トンネルからそのまま宇和島方面に向かうが、土佐くろしお鉄道線は川奥トンネルに入るとループを描きながら川奥信号場の真下(というより崖下(^^; )に出てくる。これが、鉄道ファンなら誰でも(?)知っている川奥ループ線で、このループ線は全国で唯一の第3セクター線のループ線である。
次の若井が戸籍上での予土線と土佐くろしお鉄道線の分岐点である。
若井はホームが片面にしかない、交換設備も駅舎も無い駅で、実質的な分岐点でもないので、単なる中間の子駅のようである。
川奥信号場からこの若井までは2キロ強あるが、この区間はJR予土線と土佐くろしお鉄道線の二重戸籍区間であり、JR線と第3セクター線との二重戸籍区間というのは極めて珍しいケースである。
事実上の予土線の起点が窪川。特急も全列車が停車する。
この日は窪川までにしておく予定であったが、窪川到着時点でまだ15時半、、、、、
ちょっと余裕があるので、その先土讃線の方に歩を進めることにした。