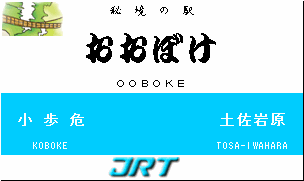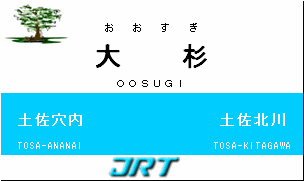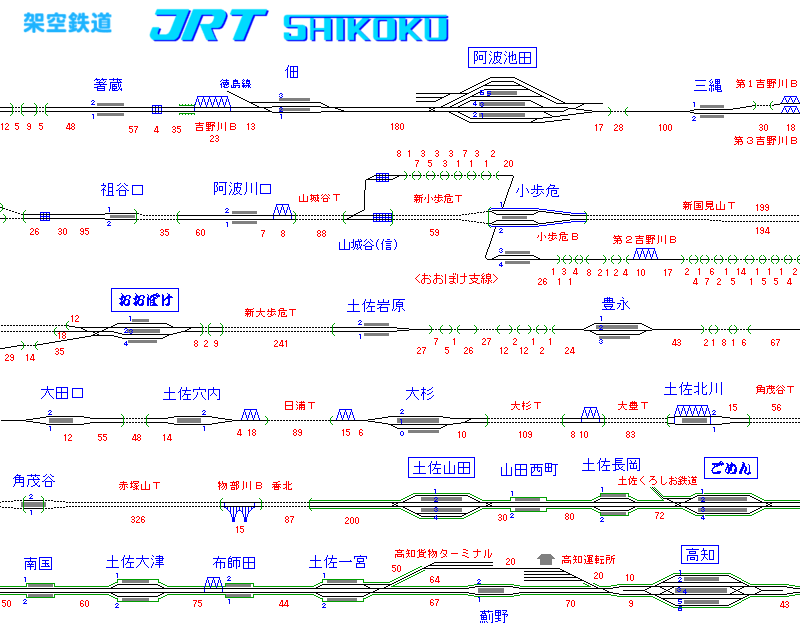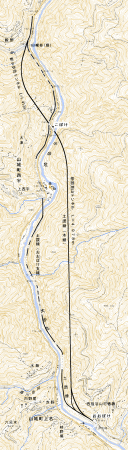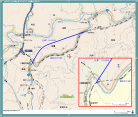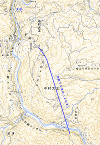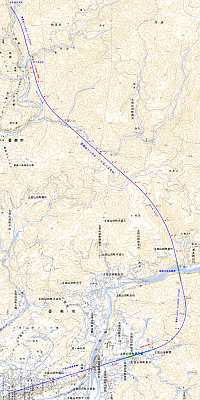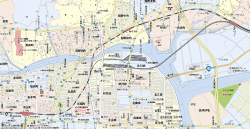<概要>
阿波池田〜土佐山田間は有数のトンネル地帯で、この区間だけで48カ所のトンネルがあり、その総延長は約40kmに及ぶ。
かつては全区間複線だったこの区間は、採算性の問題から虫食い的に単線化され、その後再度複線化された区間もあり、需要とコストの微妙なバランスが図られている。
阿波池田から次の三縄までは単線。
三縄から先の阿波川口までの間も、一時複線化されていたのが単線化されたが、時刻修正により対向列車離合箇所の変更などに対応するため、単線化後も留保していた線路用地を生かして、EC500系投入などによる旅客増といった好材料を背景に、2007年7月改正から再度複線化された。
三縄を出ると、下り線は単線化の際に廃止されのち復活した旧線のルート(現JR土讃線のルート)をたどり、一旦山側左に切り込んでからR300の城倉山トンネルに入り、第三吉野川橋梁(下り線)を渡って氷見山トンネルに突入、トンネル途中で上り線と平行し、出たところで上り線に並ぶ。
一方の上り線は、三縄を過ぎると600Rの右カーブで向きを変えて吉野川を斜めに渡り(第三吉野川橋梁(上り線))、そのまま対岸の猫坊トンネル(652m)に入って、出たところで氷見山トンネルを抜けてきた下り線と合流する。この上り線の方が複線化の際に敷設された路線となる。
祖谷口駅は移設され、一部が下川トンネル(1,087m)の中に入っている。
下川トンネルは当初複線で開通していたのが一時単線化されていただけであるため、2007年7月改正での再複線化の際はそのまま線路を増設した。
阿波川口の場内はそのまま銅山川橋梁に繋がり、渡ったところですぐに山城谷トンネル(2,180m)に突入する。
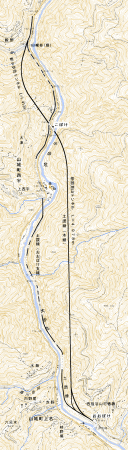 |
山城谷トンネルを抜けた先、白川橋梁(116m)のあたりで、線路は複線の本線と単線の支線に分かれる。
本線は白川橋梁からそのまま真っ直ぐ対岸の山腹に向かい、新小歩危トンネル(1,413m)に突入する。
トンネルを抜けると小歩危橋梁(287m)を渡り、この小歩危橋梁上に、本線の小歩危駅が設置されている。
小歩危橋梁を渡って対岸の新国見山トンネル(4,978m)に入ると、3000Rの緩曲線を描いた後、おおぼけ駅の手前までを一直線に抜ける。
新国見山トンネルは、旧下り線として使用していた旧国見山トンネル(3,452m)との合流地点までは、通常の複線トンネルで、その先は上下線別々の平行トンネルとなっている。
廃止された旧国見山トンネルの一部区間は、保線基地や非常時の待避所などとして活用されている。
新線区間の総延長は約6.6kmで、旧線よりも約0.3kmほど距離が短縮され、もっとも急なカーブが旧線の300Rから600R(新国見山トンネル出口付近:上り線のみ)に緩和された。
一方旧線については、白川橋梁付近に設けられた山城谷信号場から分岐し、同橋梁から小歩危駅を経て第二吉野川橋梁までの区間を単線化したうえ、第二吉野川橋梁からおおぼけ駅までの単線(旧上り線)と併せて、臨時・イベント列車専用線(愛称「おおぼけ支線」)として、継続使用している。
阿波川口〜おおぼけ間を利用する場合の運賃計算には、実際の乗車経路にかかわらず、距離の短い新線区間の営業キロ程を適用することとしている。
おおぼけ支線は、ほぼJR土讃線のルートを辿る。
支線の小歩危駅と本線の小歩危駅は通路で結ばれている。
本線と支線では雨量規制の基準値が異なるため、支線のみ運転抑止となる状況もあり得る。
なお、この旧線区間は2017年3月4日改正を機に電化設備が撤去されて非電化区間となり、同区間を経由するトロッコ列車の牽引車両が気動車化された。
(地図出典:国土地理院・1/25000地形図「杉・繁藤」)
|
おおぼけを出て、玉ノ追トンネル(75m)を抜けると、新大歩危隧道(6,183m)に突入する。新大歩危隧道は旧大歩危隧道(=JR土讃線大歩危隧道)と阿波池田側坑口は同じだが、トンネル途中から600Rで一旦吉野川河岸に出る旧隧道に対し、1000Rという大きな曲線で土佐岩原の直前までトンネルで突き抜ける。
土佐岩原から土佐穴内まではほぼJR土讃線のルートをトレースする。このうち、大田口〜土佐穴内間は腹づけ複線区間で、それ以外は単線区間となっている。
土佐穴内を出ると、線路はそのまま真っ直ぐ抜けて穴内川を渡って日浦トンネル(2,885m)を抜け、再び穴内川を渡って大杉に到着する。
これが複線化の際に上り線として建設された路線で、廃止された旧下り線はJR土讃線のルートをほぼそのまま踏襲している。
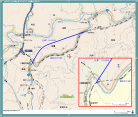 (地図出典:マピオン電子マップ) (地図出典:マピオン電子マップ)
大杉から土佐山田までは、旧線を全て捨てて全面的にルートの変更が行われた区間となっている。
大杉を出ると大杉トンネルに入るが、JRTの大杉トンネル(2,725m)は入口から1200RのS字を描いた後は、第四穴内川橋梁から大豊トンネル(2,067m)入口に至るまでを一直線に抜けるルートとなる。
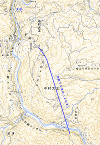 (地図出典:国土地理院・1/25000地形図「杉・繁藤」) (地図出典:国土地理院・1/25000地形図「杉・繁藤」)
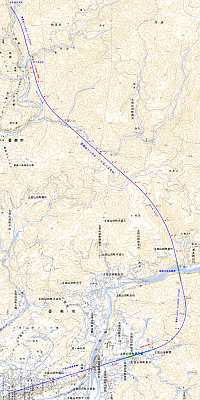 |
土佐北川からは3200Rの曲線で角茂谷までを一本のトンネル(角茂谷トンネル/L=1,397m)で抜ける。
線路変更に合わせて角茂谷駅は高架駅となり、駅の一部が前後のトンネルの中に入っている。角茂谷駅の下り方場内から、土讃線最長の赤塚山トンネル(8,145m)に突入する。
同トンネルは、2014年3月に予讃線の三方が森トンネルが開通するまでは、道路トンネルも含めて四国最長であった。
トンネルに入るとほどなく2000Rのカーブを描きつつ20‰の勾配を下り、約3kmの直線区間の後、4000Rの緩曲線で南南東に向きを変え、ちょうど旧香北町と旧土佐山田町の境界付近でトンネルを出るとともに、物部川を川面から約100mの高さで渡る(物部側渓谷橋梁:L=554m)。
そのまま対岸に渡って香北トンネル(1,612m)に入り、1,200Rの曲線で西南西に方向転換する。
その先は、高知テクノパークのすぐ南側に抜けて勾配も15‰に変わり、鏡野公園の南あたりを経て再び物部川を渡った(物部川神母ノ木橋梁)のち、高架の土佐山田に至るまでの約5kmを一直線に駆け抜ける。
この新ルートの完成によって繁藤と新改の両駅は廃止された。 また大杉〜土佐山田間については、最急曲線が300Rから1,200Rになったほか、最大高低差がそれまでの約320m(繁藤駅と地平の土佐山田駅:約13km)から約280m(角茂谷駅と高架の土佐山田駅:約16km)となり、最急勾配が25‰から20‰に緩和された。
(地図出典:国土地理院・1/25000地形図「繁藤・土佐山田」)
|
土佐山田からはほぼJR土讃線のルートをトレースするが、高知平野を走る伊野までの区間は水害対策の一環として全て高架化されている。
土佐一宮からは、高そね町に移転した高知貨物ターミナル駅と、北川添町に移転した高知運転所へ通じる支線が分岐する。
薊野の先、久万川大橋を渡ったところで運転所からの支線が合流し、高架のまま高知駅に到着する。
駅に隣接していた運転所と貨物駅は、1978年10月の高知駅高架化の際に、高そね町と北川添町に移転している。
当初は高知運転所へは高知駅側からしか入れなかったが、その後高知貨物ターミナル駅から運転所へ抜けるルートが作られ、結果、土佐一宮側からも運転所には入れるようになっている。
なお、高知駅側から運転所への路線はJRT四国の路線だが、土佐一宮から高知貨物ターミナル駅までの路線はJRT貨物の保有となる。
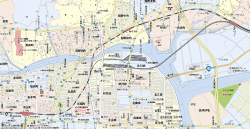 (地図出典:マピオン電子マップ) (地図出典:マピオン電子マップ)
閉塞・信号方式
| 区間 | 閉塞方式 (切替時期) | 信号方式 |
| 阿波池田〜大杉 | ATS-SPS (2007.7.1.) | 3灯 |
| 大杉〜土佐山田 | ATS-SPS (2004.3.13.) | 5灯 (GG現示付) |
| 土佐山田〜高知(伊野) | ATS-SPS (2006.4.1.) | 5灯 (YG/YY現示付) |
この区間のCTC化は1967年で、これは本線級では国鉄初であった。
<列車>
この区間の特急列車は、「南風」16往復と「しまんと」9往復「土佐」が1往復に加えて、徳島線直通の「よしの川」3往復が加わり、その全て単独運転となるため、特におおぼけ〜土佐山田間では、特急列車の本数が普通列車の3倍という状況となっている。
「南風」がEDC510系電気式バイモード車、「しまんと」がEC500系とDC500系の1000番台車、「土佐」がEC710系、そして「よしの川」はDC500系1000番台車による運転点となる。
最高速度は基本的に130km/hであるが、大杉〜土佐山田間については、「南風」「しまんと」「よしの川」が最高速度160km/h、その他は回復運転時のみ同145km/hが許容されている。
普通列車は、電車については全てEC310系に一本化され、朝夕に編成列車がある以外は単行ワンマンとなる。
高知都市圏輸送区間となる土佐山田〜高知間は、土佐山田折り返しで土佐市・佐川・須崎方面直通のEC310系による電車列車のほか、土佐くろしお鉄道から乗り入れの気動車による快速列車(朝夕の一部は各駅停車)が加わり、日中ほぼ15分間隔で普通列車が走行する。
また、阿波池田〜おおぼけ間は徳島線からの気動車普通列車が朝夕に乗り入れている。
夜行快速「ムーンライト土佐」はEC320系20000番台3両編成で、行楽シーズン等は適宜増結される。
阿波池田〜おおぼけ間に運転される「トロッコおおぼけ」号は、DC310系+EDC120系トロッコ車で編成される。
阿波池田〜高知間のリバイバル臨時快速「DF50やまなみ」は、旧型客車風な外観のDC100系ハイブリッド気動車4両編成をDF50形が牽引する。
さらに、旧国鉄形車両を模したレトロ調車両で運転される臨時急行「土佐」と臨時快速「レトロやまなみ」がそれぞれ1往復設定されている。
これらの観光列車は全て、阿波川口〜おおぼけ間は電化設備が撤去されて非電化された川沿いの旧線(おおぼけ支線:単線)を走行する。
貨物列車は定期3往復と臨時1往復が走行。
最高速度120km/hの「スーパーライナーくろしお」と最高速度110km/hの「スーパーライナー土佐路」が各1往復、最高速度95〜100kn/hの「浦戸」が2往復(内1往復臨時)の合わせて4往復が運転されている。
編成は「スーパーライナー土佐路」が10両、それ以外は全て8両が所定となっており、急峻な区間を高速で抜けるために全てEH161形の牽引となる。
|