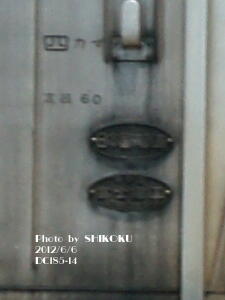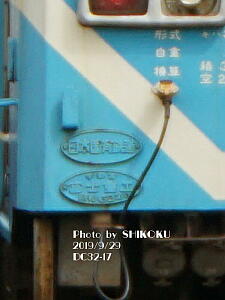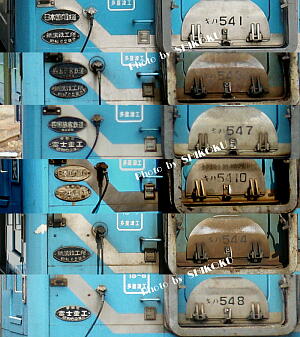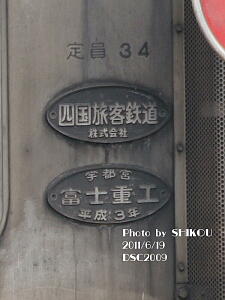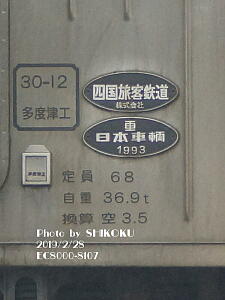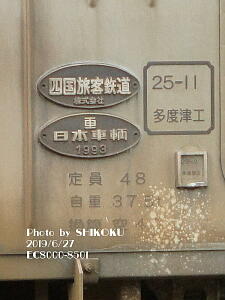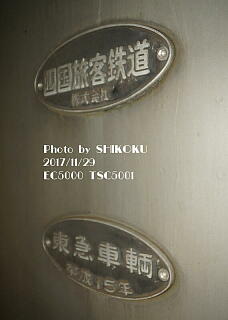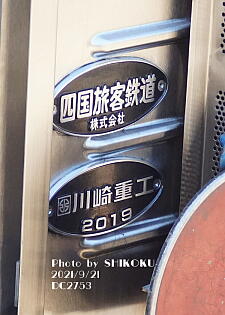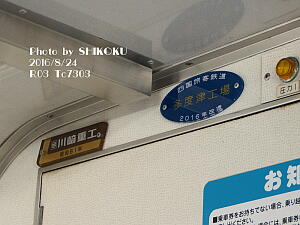�`�����Ԃ̏ꍇ�`
|
�@�����ԗ��̏ꍇ�A���Ă͊��ɏq�ׂ��悤�ɐ����Җ��͂��̂܂܂ʼn����҂̖���lj����Ă����̂����S����̃X�^�C���ł��������A���Ȃ��Ƃ��i�q�l���ɂ����Ă͎ԑ̊O�ɂ͉������Ǝҁi�H��j�̖��̒lj��͍s���Ă��Ȃ��B �@�Ȃ��A�I���T�O�n�u�A�C�����h�G�N�X�v���X�l���v�͍��S����̉����ł��邱�Ƃ���A�����ł͏��O����B
�@�����ԗ��̏ꍇ�́A��Ԃ����Д����Ԃ̏ꍇ�͖������̂܂܌p���g�p���A���S�����Д����҂̏ꍇ�͎��Ж��Ɍ������Ă���悤�ł��邪�A�������e�̑召�ɂ���Ă͌������Ă��Ȃ��P�[�X������i�u�A�C�����h�Q�v���j�B �@�������Ă���P�[�X������ƁA�P�X�X�X�`�Q�O�O�P�N�����̂P�P�R�n�ł́u����v�\�L�ŁA�Q�O�P�U�N�����̂V�Q�O�O�n��L���P�W�T�`�ł́u�����v�\�L�ɂȂ��Ă���A�V���Ԃ̖��\�L���ύX���ꂽ�Q�O�O�R�N�����ɕς���Ă���A���낪�����B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||