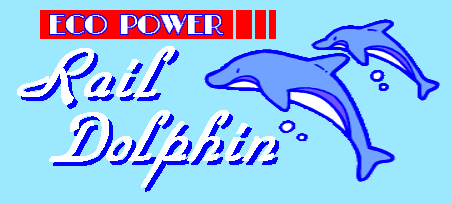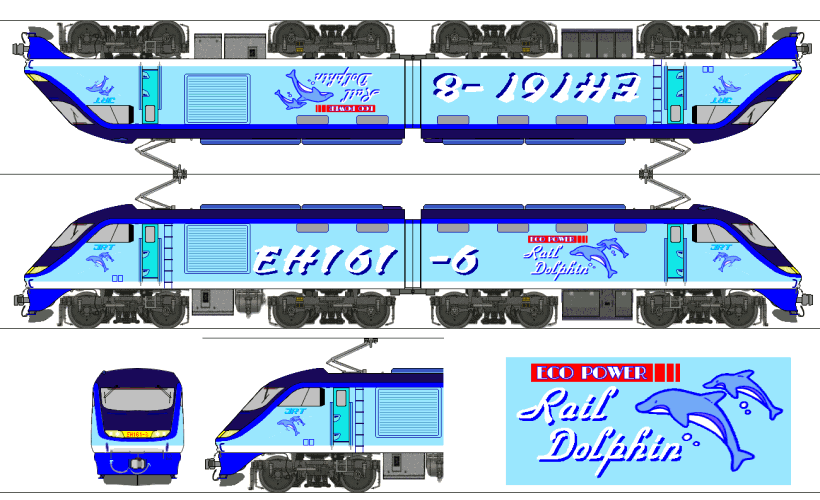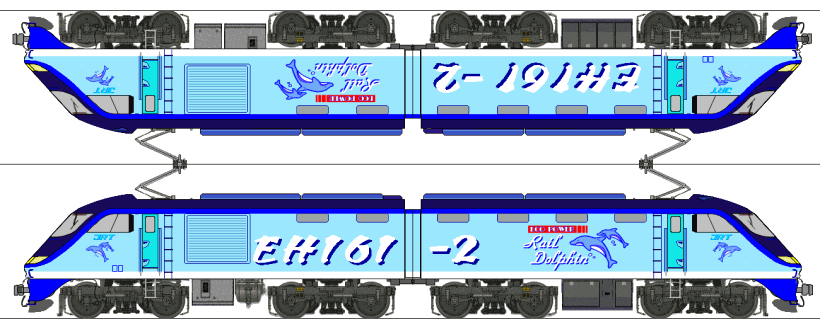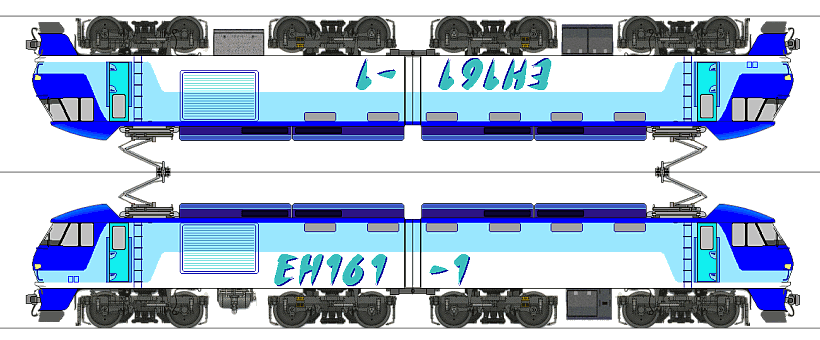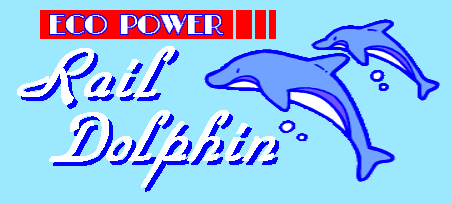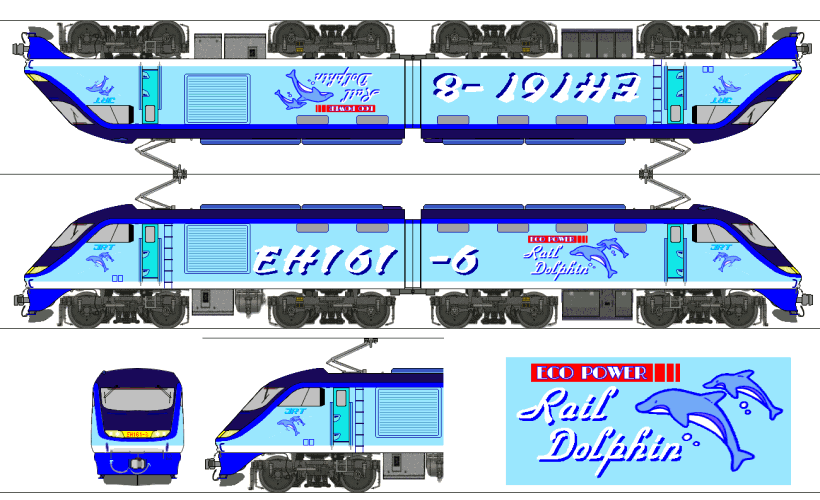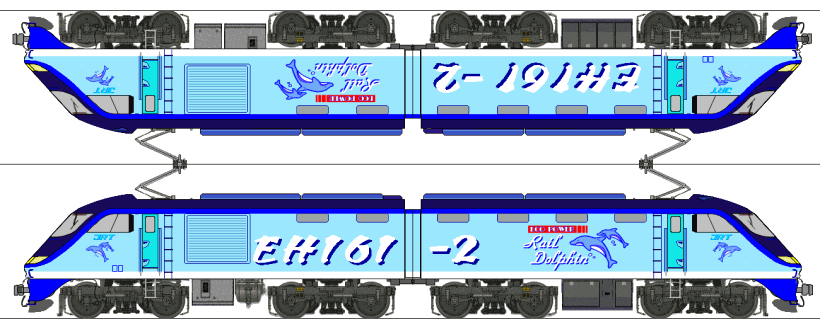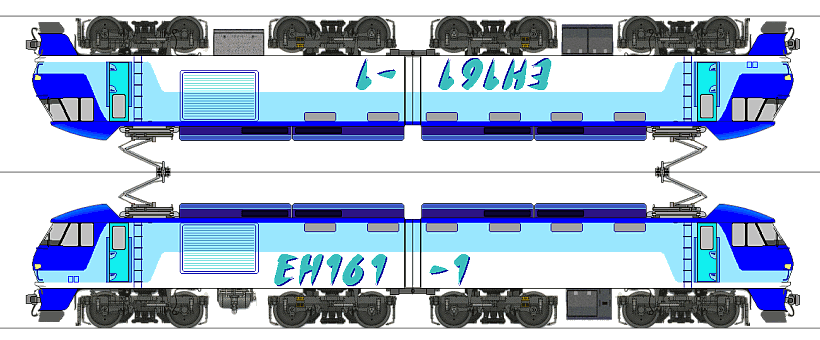EH161形
高速貨物用 直流電気機関車
ECO POWER
「Rail Dolphin」
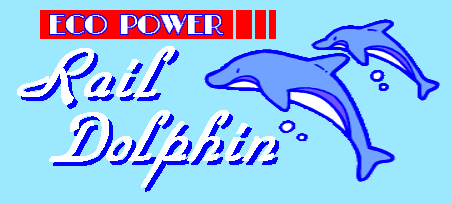 6号機〜(第2次量産車〜)
6号機〜(第2次量産車〜)
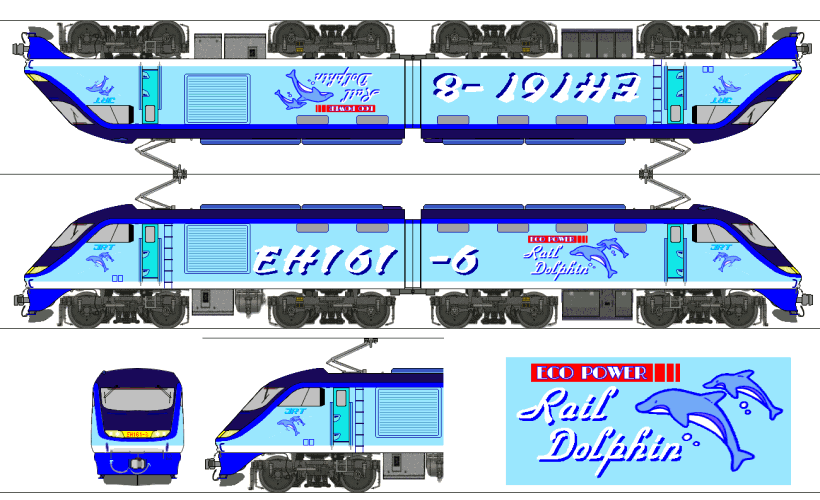 主要寸法入り高精細版(PDF:186KB)
2号機〜5号機(先行量産車/第1次量産車)
主要寸法入り高精細版(PDF:186KB)
2号機〜5号機(先行量産車/第1次量産車)
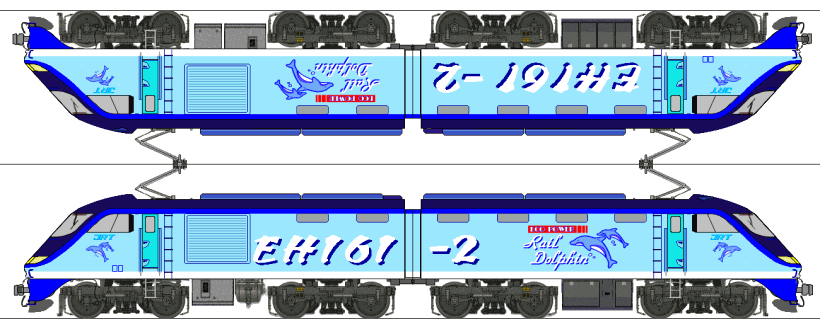 1号機(先行試作車)
1号機(先行試作車)
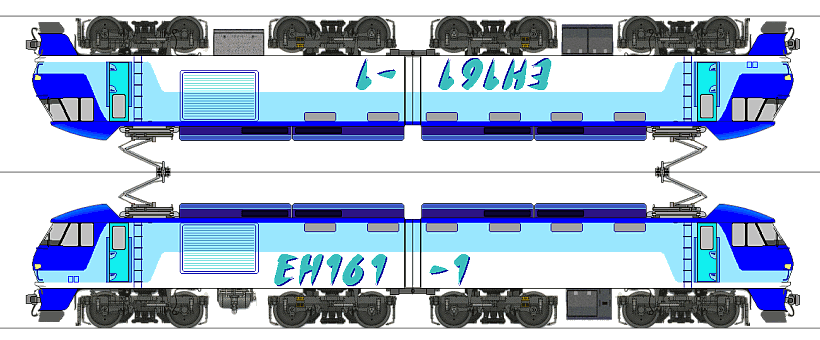
予讃線・土讃線における、将来の高速貨物列車の速度向上および輸送力増強を睨み、さらに現在工事中の予讃線・小松−松山バイパスの完成後をも視野に入れた、高速貨物列車用電気機関車。
JRT−EF161形の高性能版、あるいはJR−EH200形の高速版という位置づけとなる。
EF161形はもとより、EF66形150番台車の後継機ともなる、「四国スペシャル機」である。
目標とした主な性能は以下の通り。
(1)将来開通する小松−松山バイパスにおいて、14両編成700トン列車(*1)を牽引して、連続12‰勾配を110〜120km/h以上で登坂できること。
(2)小松−松山バイパスの下り勾配区間、土讃線 角茂谷〜土佐山田間の下り勾配区間等においては、130km/h以上の連続高速走行が可能であること。
(3)12両編成600トン列車(*2)を牽引して、土讃線の25‰勾配&300R曲線区間において単機で起動・登坂可能であること。
(4)土讃線 土佐山田〜角茂谷間の連続20‰勾配区間において、12両編成600トン列車(*2)を100km/h以上で、8両編成400トン列車を120km/h以上で牽引登坂できること。
(5)予讃線・土讃線の小断面トンネルに対応していること。
(6)抑速ブレーキ等の勾配対策機器を搭載していること。
(7)将来のさらなる性能向上が可能であること。
(8)最急250Rの通過が可能であること。
(*1)計画当時、新居浜〜松山間の貨物列車は、最長で12両編成600トンだが、将来の時間短縮に伴う需要増による輸送力アップを見込んでいる。
(*2)計画当時、土讃線貨物列車は、牽引機EF161形の性能と線路有効長の関係から、8両編成400トン牽引に制限されているが、将来の貨物需要増と線路改良による輸送力アップを見込んでいる。
以上の条件から、最低限必要な出力を4,300kWhと算出(歯数比5.0の場合)。
連続高負荷高速走行を行うため、定格速度を高く設定する必要があることから、歯数比を4.65とした場合は、4,500kWh以上の性能が必要となる。
現在、土讃線と予讃線においては、18000系9両編成の特急「しおかぜ」と、EC500系7両編成の特急「南風」が、いずれも編成定格出力4,800kWhであることから、若干の余裕を見込んだ上でそれらと出力を合わせ、連続定格出力を4,800kWhに設定した。
その上で、高速走行による軌道への影響を抑え、また土讃線の一部区間における軸重制限をクリアするために軸重を16tに抑えながら、特に土讃線山間部における秋季の落葉ならびに冬季の積雪対策として充分な粘着力を確保するため、2車体連結の8軸駆動とした。
また将来、さらなるスピードアップと輸送力増強を要請されたときにも対応できるよう、電動機は700kWh(30分定格750kW)設計のものを、当面600kWhとして使用することとした。
歯数比は4.65とし、許容最高速度は130km/hとした。
但し、現時点ではJRT四国管外の区間、特に想定する乗り入れ対象区間である東海道・山陽本線 東京〜岡山間においては、4,000kWhを超える大出力への対応が不十分であることから、当該区間への乗り入れの際には限流値スイッチを自動で切り替えることにより、出力を4,000kWh程度に抑えることとする。
限流値スイッチはオフの状態を通常値とし、JRT四国の保安設備である、ATS−SS、およびATS−SP信号を受電できない状態となった場合(管外に出た場合)に、自動的にオンに切り替わるよう設定される。
主幹制御器は、現在四国内を走行しているEF66−150形、ならびにEF161形に合わせて、横軸2ハンドル電気接点式とする。
制御方式は、1C1M個別制御式のIGBT−VVVFインバータ制御とし、マスコンは疑似18ノッチ刻みの無段式。
ブレーキは応荷重・応速度増圧付 電気指令式空気ブレーキとし、抑速回生ブレーキ(回生失効時は発電ブレーキに自動切替)を搭載。
パンタグラフはEF210形などと同じFPS4形、乗務員室空調はEF161形と同一、その他の補機類もEF210形などと極力共通化し、保守点検等の簡略化を図っている。
2007年7月ダイヤ改正に合わせて先行試作車(1号機)が登場し、各種試験を兼ねた営業運転を行ったのち、2008年から量産車が登場した。
量産車の登場に合わせて、1号機は一部仕様変更改造が行われている。
<量産車(2〜5号機)>
先行試作車の作成後に、一部仕様変更等が盛り込まれたため、それらを織り込んだ量産前提の先行量産車を、2007年12月に2号機として投入した。
これに合わせて、新たに「ECO POWER 『Rail Dolphin』」の愛称とロゴを作成した。
主な変更点は以下の通り。
◆ 前頭部をくさび形のスラントノーズとするなど、主として以下に掲げる内容の大幅なデザイン変更を行った。
・解放てこにカバーを付し、作業用ステップと一体化した
・前照灯を高輝度白色HID4灯とした。
・前照灯の間は黄色の警戒色とするとともに、形式表記プレートを配した。
・LED式の後部標識灯を横列化して、室内天井配置とした。
・EC500系と同様な、車体側面からそのまま続く屋根カバーを設けて、側面デザインの一体感を向上させた。
◆ デザイン変更に伴い、全長を0.5m延長した。
◆ また運転台乗降ステップの位置との関係から、台車中心間距離を0.5m延長した。
◆ 排障器(スカート)の厚みを増して、乗務員室の拡大と併せて事故対策を強化した。
◆ パンタグラフを塩害対策を強化したFPS4B形に変更した。
◆ 機器室内の配置を見直し、保守性を向上させた。
◆ モニタ装置について、MPU変更ならびにLCDを大型化し、応答性と使い勝手の向上を図った。
◆ 初期の目標を上回る牽引力が確認できたことから、歯数比を4.65から4.5に下げて高速域の特性を向上させた。
◆ 回生ブレーキについては、必要性や使用頻度を考慮のうえ廃止して発電ブレーキのみとし、併せて放熱器の容量をアップした。
運転台乗降用の乗務員室扉の位置が変わったことにより、運転台への乗降用ステップがそれまでの台車取付から車体取付収納式に変更となり、これに合わせて補機類の配置が変わったため、運転台側の台車形式が変更となっている(向きも逆になっている)。
このほかの仕様は1号機と同一となっているが、車体全長とデザイン変更によって機器室の面積などが変わったため、一部の機器類についてユニット化を図ったり、配置の変更などを行っている。
2008年3月改正では、3〜5号機の3両が2号機と同一仕様で増備され、東京(タ)〜高松(タ)間の「スーパーライナー四国路」と、東京(タ)〜高知(タ)間の「スーパーライナー土佐路」で定期運用を開始した。
これに合わせて1号機も量産車と共通仕様化(車体はそのまま)改造を行い、共通運用としている。
<第2次量産車(6号機〜)>
2009年3月ダイヤ改正に合わせて、第2次量産車(6〜10号機)が登場。
基本仕様などに変更はないが、下記の通り細部に改良が加えられている。
◆ 運転台への乗降ステップが、従来の車体取付から台車取付タイプに変更となった。
これに合わせて、前位側第1台車と後位側第4台車の形式名がF−DT161Cに変更となった。
◆ 屋根カバーの高さが20mm低くなって最大車体高が3,920mmとなった。
◆ パンタグラフは一部部材の変更により、FPS4Cに形式名が変更となるとともに、パンタグラフ折りたたみ高さが10mm低くなって3,890mmとなった。
◆ 車体側面の屋根昇降用梯子を、片側面に付き1カ所のみとした。
◆ その他、一部電子機器を改良型に置き換えて、保守性と信頼性を向上させた。
2010年3月ダイヤ改正に合わせて、さらに3両(11〜13号機)が登場している。
合わせて総勢13両が、JRT貨物・高松機関区に配置されて、本州〜四国間ならびに四国内の高速貨物列車に運用されている。
| 形式 | EH161形 |
1号機
(先行試作車) |
2号機〜5号機
(先行量産車)
(第1次量産車) |
6号機〜
(第2次量産車) |
| 最大寸法 | L | 24,500 mm | 25,000 mm |
| W | 2,930 mm | 2,960 mm |
| H | 3,940 mm | 3,920 mm |
| パンタグラフ折畳み高さ | 3,900 mm | 3,890 mm |
| 運転整備重量 | 128.0 t |
| 軸配置 | B0−B0 + B0−B0 |
| 車体 | 普通鋼 |
| 制御方式 |
1C1M個別制御式
IGBT−VVVFインバータ制御 |
電動機形式
出力 |
MT162
600kw(1時間定格)×8 |
| 定格引張力 | 275KN |
定格速度
(1時間定格) |
75.0km/h
(*1) | 77.5km/h |
| 歯数比 | 4.65 (*1) | 4.5 |
| パンタグラフ形式 | FPS4 (*1) | FPS4B | FPS4C |
| ブレーキ方式 | 応荷重・応速度増圧付 電気指令式空気ブレーキ |
回生ブレーキ併用(*1)
発電ブレーキ併用 | 発電ブレーキ併用 |
| ブレーキ装置 | 車輪ディスク |
| 台車 | 形式 |
DT162
DT162S |
F−DT162B
F−DT162S |
F−DT162C
F−DT162S |
| 固定軸距 | 2,600 mm |
| 車輪直径 | 1,120 mm |
| 台車中心間距離 | 6,000 mm | 6,500 mm |
| 許容最高速度 |
130km/h
(設計:145km/h) |
| 曲線通過速度 |
450>R:本則+5km/h
R≧450:本則+10km/h |
| 冷房装置 |
4,000 kcal/h × 1
強制換気付き |
(*1) 2号機〜(量産車)と共通仕様化改造済み
検索サイトから直接来られた方は、ここをクリックしてTopに移動できます